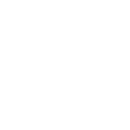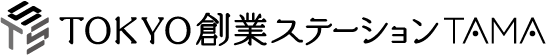新商品開発を成功に導く鍵は「顧客の声」にあり!売れる商品の作り方
新商品開発を成功に導く鍵は「顧客の声」にあり!売れる商品の作り方

本記事では、新商品開発を成功に導くための「顧客志向」の重要性をお伝えするとともに、顧客の声を正しく捉え、本当に「売れる商品」を作るための具体的な手法について、実例を交えながら詳しく解説します。
目次
「作りたい商品」と「売れる商品」はなぜ違うのか?
「これだ!」という画期的なアイデアを思いつき、情熱を込めて新商品を開発したにもかかわらず、全く売れない…。そんな経験はありませんか?多くの起業家や開発者が直面するこの課題の裏には、共通の落とし穴が潜んでいます。それは、作り手の「作りたい」という想いと、顧客の「欲しい」というニーズの間に生じるズレです。 新商品開発において最も重要な前提は、「作りたい商品」と「売れる商品」は必ずしも同じではないということです。開発者は自身の持つ技術や経験、課題意識から「これは素晴らしい商品だ」「世の中の役に立つはずだ」という強い思い込み(バイアス)を持ってしまいがちです。しかし、その情熱が顧客の本当のニーズとずれている場合、どれだけ優れた技術や機能を盛り込んでも、自己満足的な商品開発に終わってしまうリスクがあります。
誰の声を聴けば良いのか?

「顧客の声を聞く」と言っても、誰の意見を参考にすれば良いのでしょうか。ここで重要になるのが、商品を届けたい「具体的な一人の顧客像」を定義する「ペルソナ」という考え方です。
なぜ「ペルソナ」を作る必要があるのか?
ペルソナを設定する最大の目的は、開発チームのメンバー全員が「私たちは、この一人のために商品を作っている」という共通認識を持つことです。これにより、機能の追加やデザインの変更といった意思決定の場面で、「彼女(ペルソナ)ならどう思うだろう?」「この機能は、彼(ペルソナ)の課題解決に本当に役立つのか?」という一貫した基準を持つことができ、議論のブレを防ぎます。
意思決定に使えるペルソナの作り方
効果的なペルソナは、単なるプロフィール設定では終わりません。その人物が実在しているかのように、背景にあるストーリーや価値観まで深く掘り下げることが重要です。 名前、年齢、職業、家族構成といった基本情報に加え、その人の価値観、ライフスタイル、抱えている悩みや課題、情報収集の方法などを具体的に描写します。これは、実際の顧客へのインタビューやアンケート調査に基づいて作成することが成功の鍵です。

事業計画書作成には不可欠な視点! ~ジョブ理論・ペルソナ設定・カスタマーインタビューとは?~
事業計画書を作成する上で最も重要な視点は、「顧客イメージが鮮明であるか?」だと思います。顧客を深く理解することが、解像度の高いビジネスモデルを構築するための鍵となります。
ペルソナは作って終わりではない:仮説検証で進化させる
重要なのは、最初に作ったペルソナはあくまで「仮説」であると認識することです。顧客ヒアリングやMVP(Minimum Viable Product)検証を進める中で、「当初想定していた悩みとは少し違うようだ」「実はこんな価値観を重視しているのかもしれない」といった発見が必ずあります。その新たな気づきを元に、ペルソナを柔軟に修正していくことが不可欠です。ペルソナを定期的に見直し、進化させていくことで、開発チームの顧客理解度は深まり、より現実に即した「売れる商品」開発に繋がっていきます。
ペルソナ具体例①働く女性向けのグルメサンドイッチ専門店
氏名: 高橋 美咲(たかはし みさき)
年齢: 32歳
職業: IT企業で働くマーケター(チームリーダー)
ライフスタイル: 都心で一人暮らし。仕事が忙しく、平日の自炊は難しいが、健康と美容には気を使いたい。週末はヨガに通ったり、友人とカフェ巡りをするのが楽しみ。
課題・悩み: 「忙しいランチタイムでも、手軽に栄養バランスの取れた食事がしたい」「コンビニ食や外食ばかりでは罪悪感がある」「午後の仕事のために、ちゃんと満足できて、かつヘルシーなものが食べたい」
ペルソナの一言: 「ここのサンドイッチなら、手軽なのにちゃんと野菜も摂れて嬉しい。午後の仕事も頑張れる。」
ペルソナ具体例②中小企業向け勤怠管理SaaS
氏名: 鈴木 誠一(すずき せいいち)
年齢: 45歳
職業: 従業員30名ほどの製造業の総務部長
ライフスタイル: 妻と高校生の子供2人の4人暮らし。趣味は週末のゴルフ。PCスキルは基本的な操作なら問題ないレベル。
課題・悩み: 「タイムカードの集計と給与計算に毎月膨大な時間がかかっている」「法改正への対応が大変」「従業員からは有給休暇の申請がしづらいという声も上がっている」「ITツールを導入したいが、操作が複雑だと現場が混乱しそうで不安だ」
ペルソナの一言: 「とにかく、毎月の面倒な作業から解放されたい。誰でも簡単に使えて、ミスがなくなるならすぐにでも導入したい。」
顧客の「インサイト」を引き出すには?
顧客の真のニーズを指し示してくれるインサイト(顧客や消費者の隠れた本音)を掴むためには、ヒアリングのやり方に工夫が必要です。
- - 顧客にとっての価値を問い続ける
「この機能が欲しいですか?」といった直接的な質問だけでは、表面的な答えしか得られません。「なぜそう思うのですか?」「それによって、あなたのどんな課題が解決されますか?」といった質問を繰り返し、顧客自身も気づいていないような潜在的な価値観や欲求を掘り下げていくことが重要です。
- - インサイトが得られるヒアリングと分析
インタビューは仮説を検証する場であるとともに、発見の場でもあります。相手の話を真摯に傾聴し、共感することで、深いインサイトが得られます。得られた発言は、事実、解釈、課題、ニーズなどに分類して分析し、商品の価値へと繋げていきます。

創業者必見!TOKYO創業ステーションTAMAのテストマーケティング支援を最大活用する方法
一般的に新しい製品やサービスで世の中に貢献したいという前向きな想いをもって創業される方は多いのではないでしょうか。 これまでのご経験や積み重ね、色々なアイデアを具体化し、製品やサービスを形にしていきますが、創業者が直面する最初の壁として以下のような共通点があります。
MVP検証で失敗リスクを最小限に

アイデアをすぐに完璧な製品にするのではなく、まずは「MVP(Minimum Viable Product)」、つまり「顧客の課題を解決できる最小限の機能を備えた製品」を素早く作り、顧客の反応を見ることが重要です。
- - MVPの作り方と検証プロセス
顧客ヒアリングで得られたインサイトを元に、解決すべき最も重要な課題に絞ってMVPを開発します。そして、そのMVPを実際にペルソナに近い顧客に使ってもらい、フィードバックを収集します。
- - 支払い意思の確認を忘れずに
MVP検証で非常に重要なのが、「もしこの製品が完成したら購入したいですか?」「いくらなら購入しますか?」といった支払い意思を確認することです。「いいね」「あったら使うかも」といった好意的な意見だけでは、ビジネスとして成立するかは分かりません。顧客が身銭を切ってでも欲しいと思うか、その熱量を測ることが、製品の市場価値を正確に見極める上で不可欠です。
MVPのその先へ:MSP(Minimum Sellable Product)の活用
MVPで顧客の課題を検証した後は、実際に「販売可能な最小限の製品」、すなわち「MSP(Minimum Sellable Product)」へと進化させるアプローチも効果的です。
- - MSPとは何か?
MVPが「学習」や「仮説検証」を主目的とするのに対し、MSPは「実際に販売すること」を目的とします。顧客がお金を払ってくれるレベルの品質や機能を備え、課金や決済の仕組みまで実装した製品です。販売を伴う「テストマーケティング」の実行や、「β(ベータ)版」のリリースによって市場に投入されます。
※本記事で記載の「テストマーケティング」では、販売等を前提にしていますが、TOKYO創業ステーションTAMAで実施する「テストマーケティング支援事業」では、支援内容に「販売行為」「個人情報収集」等は含まれておりません。 - - MSPのメリット
MSPを市場に投入することで、単なる好意的なフィードバックではなく、「実際の売上」という最も確実な形で市場の需要を測定できます。これにより、事業の収益性を早期に検証し、本格的な開発やマーケティングへの投資判断をより確かなものにすることができます。
まとめ

新商品開発の成功は、作り手の情熱だけでなく、顧客の声に真摯に耳を傾け、そのインサイトを製品に反映できるかにかかっています。「作りたいもの」から「顧客が本当に求めているもの」へと視点を転換し、ペルソナ設定、顧客ヒアリング、そしてMVPやMSPを通じた検証プロセスを丁寧に実行することが、成功への確実な一歩となります。
新商品開発・マーケティング戦略のご相談は、TOKYO創業ステーションTAMAへ
TOKYO創業ステーションTAMAの「Planning Port TAMA」には、 新商品開発から、マーケティング戦略・事業計画書に関するご相談(プランコンサルティング)ができる専門コンサルタントが多数、在籍しております。相談は無料で電話やZoomでの相談も可能です。
※プランコンサルティングの利用方法はこちら
https://startup-station.jp/tn/services/consultation/planconsulting/#howtouse
メンバー登録はこちら
創業・開業の相談はこちら
TOKYO創業ステーションTAMAには、起業全般に役に立つセミナーや先輩起業家による起業相談を行う「Startup Hub Tokyo TAMA」と、ターゲットを絞ったセミナーや事業プラン作成を専門コンサルタントがコンサルする「Planning Port TAMA」の2施設があります。どちらの施設のセミナー受講、ご相談も無料です。また、電話やZoomでの相談も可能です。是非、ご利用下さい。
また、TOKYO創業ステーションTAMAを初めてご利用される場合は、「Startup Hub Tokyo TAMA」をご訪問下さい。施設の利用法を含め、ご利用者様の起業に向けた疑問・お悩み事に合った、施設や相談員の活用法についてアドバイスを実施しています。是非、ご利用下さい。お越し頂ける日を楽しみにしております。
メンバー登録はこちら
施設情報・関連ページ
TOKYO創業ステーションTAMA
〒190-0014 東京都立川市緑町3-1
GREEN SPRINGS E2 3階
電話:042-518-9671
TOKYO創業ステーションTAMAは、東京都内で起業を目指すみなさんを応援する創業支援施設です。起業相談、事業計画書策定支援、イベント・セミナーのご参加、テストマーケティング出展など、すべてのサービスを無料でご利用いただけます。

 著者:辰野 博一(たつの ひろかず)
著者:辰野 博一(たつの ひろかず)
TAMAプランコンサルタント
大手電機メーカーでオーラルケア商品の商品企画を担当し、20・30代OL向けの携帯型電動歯ブラシが、市場規模を2倍にするヒット商品となる。メーカー退社後独立し、早稲田大学アントレプレナーシップセンターや公的インキュベーション施設などでの起業相談、経営相談に従事し、研究者や学生、研究開発型企業の経営者、スタートアップ企業の経営者との面談に年間延べ100件以上対応している。2020年からはNEDO NEP事業のカタライザーとして、研究シーズの事業化支援にも従事。
また、2015年より現在まで埼玉県本庄市での「ゼロから始める創業スクール」の講師として、プログラム検討・講義・ビジネスプランへのフィードバックを担当し、起業を目指す方々をサポートしている。
中小企業診断士。修士(エネルギー科学/商学)。ユニコーンファーム社Startup Advisor Academy認定スタートアップアドバイザー。専修大学経営学部兼任講師(「デザインと経営」)。
※本記事は、個人の意見・見解です。また、本記事で紹介している情報は、執筆時点のものであり、閲覧時点では変更になっている場合がございます。